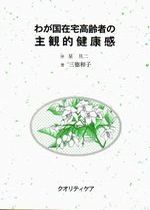|
高齢者に加齢による身体的痛みや、障がいがあったとしても、主観的に自分は健康であると自覚し、個人個人の人生や生活を楽しみながら生きている姿は、高齢者自身だけでなく、我々にも生きることへの希望と勇気と安心を与えられる。そのことは社会全体の安寧に寄与することであろう。
そこでこの論文では、高齢者の主観的健康感について、
Ⅰ・Ⅱ章では、主観的健康感と生存の関連をレビューし、
Ⅲ章では、2002年に公式翻訳がなされた直後の国際生活機能分類を用いて主観的健康感と心身機能と身体構造・活動・参加の各構成因子とその背景にある環境・個人との関連を数量化により総合的に観察した。
さらにⅣ・Ⅴ章では高齢者の主観的健康感の維持要因を経年的観察から探るとともに、主観的健康感と3年後の生命予後との関連を明らかにした。
(「はじめに」から抜粋)
目次
Ⅰ章 わが国在宅高齢者の主観的健康感とその経年変化に関する関連要因および生存に関する研究
第1節 主観的健康感についての背景
1.わが国の高齢者率の現状
2.高齢者の世帯と所得
3.平均寿命と健康寿命
1)要介護状況と医療費および介護保険給付費
2) 国民の不安
第2節 高齢者の健康-WHOの定義から
1.健康の概念の変遷
2.国際連盟設立から国際連合設立までの健康と健康指標
3.国際連合の設立
1)WHOの健康の定義
2)健康の定義の作成経緯
4.健康定義とその後の定義の変遷
1)健康の一元論
2)健康の二元論
3) 健康の定義の見直し
(1) 病気を中心的課題とした取り組みへの批判
(2) WHOの定義の見直し
第3節 健康の測定
健康測定の課題
Ⅱ章 主観的健康感のレビュー
第1節 主観的健康感の背景
第2節 主観的健康感とは
第3節 主観的健康感の測定
1.主観的健康感測定の背景
2.主観的健康感と生命予後の関連
1) 全死因の死亡との関連
2) 性差との関連
3) 年齢・世代との関連
4) 各死因との関連
5) 疾病発症予測および追跡期間との関連
6) 追跡期間および社会経済との関連
7) 主観的健康感の指標としての意味の解明の研究
Ⅲ章 主観的健康感の関連要因
第1節 対象と方法
1.対象
2.調査内容および調査方法
3.倫理的配慮
4.集計・分析
1) 集計と因子分析
2) モデル作成
第2節 結果
1.対象者の特性
最適モデル
2.潜在因子間の影響方向
1) 潜在因子間の直接・間接影響の強さ
2) 潜在因子と観測変数の関連
第3節 考察
1.高齢者の主観的健康感について
2.健康関連要因の定量的影響方向について
3.「社会参加」について
4.「活動(生活能力)」について
5.主観的健康感と女性について
Ⅳ章 主観的健康感の関連要因の変化
第1節 対象と調査方法
第2節 結果
1.主観的健康感
2.主観的健康感の1年6ヵ月後の変化に関連する要因
第3節 考察
1.主観的健康感の分布と1年6ヵ月後の変化
2.健康関連要因の変化と主観的健康感の改善
Ⅴ章 主観的健康感と生命予後
第1節 方法
1.調査対象
2.調査項目と分析方法
第2節 結果
1.主観的健康感の実態と関連要因
2.主観的健康感と生存との総合解析
3.主観的健康感と累積生存
第3節 考察
1.調査の限界性と課題
2.主観的健康感の実態と関連性
3.主観的健康感の生命予後予測妥当性
4.主観的健康感と死亡との関連を究明する研究課題
5.健康支援による実証疫学の必要性
6.主観的健康感に関するその他の課題
終章
第1節 まとめと結論
1.各章のまとめ
2.結論
第2節 考察
1.主観的健康感と健康指標
2.主観的健康感と関連要因
3.主観的健康感と健康政策