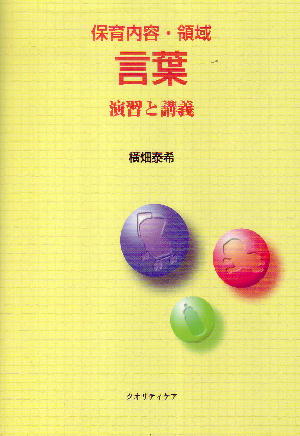
「講義と演習」というサブタイトルは、概論的な内容の講義形式の授業と、指導法的な内容の演習形式の授業の両方を示している。どちらにも対応できる内容であるが、演習形式の指導法の授業の際には、各講に示した演習問題に基づいて考察を深めていけるよう配慮した。
ところで、人間が使う言葉は癒しにもなれば、武器にもなることは周知のとおりである。これは言葉の持つ意味について考えていかなければならないことを示唆している。
たとえば、A児がB児に「そんなん、やめればええじゃろぉ!」と言う。その言葉を発したA児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉を受ける側のB児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉で繋がっているA児とB児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉を傍で耳に(目に)している保育者にとって、その言葉の意味は何なのか。これらは、言葉の意味を探っているようであり、実は保育そのものだと言っていいのではないか。言葉を育てる保育だけを考えていては、保育の本質を見誤る。あるいは見失う。保育とは、子どもの心と身体を健やかに育てることに他ならない。心が健やかに育つことが、すなわち言葉が育つことに他ならない。
本書、本科目を通して、子どもにとって何が大事なのか、保育者はどうすればいいのかを考え、
保育者としての基礎を培ってもらえたらと願っている。
本書「まえがき」より 橫畑泰希
《目 次》
1講 領域「言葉」が目指すもの
2講 言葉(ことば)とは何か
3講 保育とは何か・教育とは何か
4講 言葉の発達の基盤①─からだでおしゃべり─
5講 言葉の発達の基盤②─前言語機能─
6講 言葉の発達の様相①─乳児期(0歳から3歳未満のころ)─
7講 言葉の発達の様相②─幼児期(およそ3歳から6歳ごろ)─
8講 保育問題の成立過程
9講 言葉の保育問題とその支援
10講 読み書きの発達とその支援
11講 遊びと児童文化
12講 保育者と言葉
定価 本体 2200円+税 ISBN978-4-904363-69―0 C3047
ご注文、お問合せは、本サイトのMain menuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。
