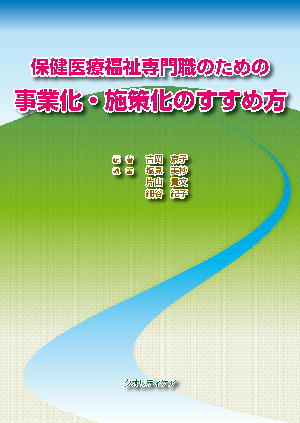
上流から地域の健康問題を支援する ご当地システムづくりをすすめるために
かつて現場で駆け出しの保健師として勤務していた頃、毎日家庭訪問を行う中で「同じような問題を訴える住民」の方にたくさん遭遇しました。私はその頃から「どうすれば住民の健康問題に基づく効果的なサービスを提供できるのか」ということを考え続けて参りました。幸いにも大学院進学のチャンスを頂き、現場のニーズに基づく政策形成をテーマとして、「事業化・施策化」という切り口で研究を始めました。インタビュー調査をさせて頂く中で、次第に「事業化・施策化をすすめるための具体的な方策がある」ということを確信すると共に、現場にはまだ十分に整理されていない暗黙知があることに気がつきました。大学院終了後に再び現場で奉職させて頂くことになり、研究で得られた知見を実践の場で検証する機会に恵まれました。現場で様々な提案や調査をさせて頂く中で、改めて事業化・施策化の方法論について再考すると共に、「事業化・施策化は神業ではなく、専門職の基本的な技術として身につけてほしい」、「専門職が住民や地域の健康問題に即した事業化・施策化を効果的にすすめるためには、知の共有化を図る必要がある」と考えるようになりました。
地域では様々な保健医療福祉に携わる専門職が、住民の健康問題を解決するために日夜個別支援に奔走しています。現場の仕事は個別支援が基本かつ中心的業務です。これは恐らく昔から変わっておらず、これからも変わることはないでしょう。しかし個別支援だけに終始していては、専門職の前に現れる困難を抱えた住民の数は一向に減りません。「皆の健康をまもる」という公衆衛生の原点に立ち返りますと、健康問題の発生そのものを予防する「より上流から支援する仕組みづくり」について考え、政策提案していくことが必要ではないでしょうか。現場に正解はありませんが、日頃の個別支援の中から今解決すべき地域の健康問題を関係者が協力して特定し、その解決に向けて前進しなければなりません。もちろん新たな仕組みづくりや従来のやり方を変えるためには、エネルギーが必要です。忙しいのに余分な仕事を増やしたくないと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、超高齢社会における莫大な医療費削減や健康寿命の延伸という未曽有の課題に取り組むためには、個々の専門職がより上流から地域の健康問題を支援する仕組みづくりについて考え、それに即した「ご当地システム化」を具現化していく必要があると思います。
本書は事業化・施策化に関する知の共有化を図るため、研究知見や実践の様々なノウハウをコンパクトに体系化しました。どこからお読み頂いても構いません。また皆様が地域の健康問題について考えたり、議論される際にお役立て頂けるように、重要なポイントやよくある失敗についてもふんだんに盛り込み、ワークシートもお付けしました。
読者の皆様が本書を読まれた後に「住民のために事業化・施策化に取り組んでみよう」と、新たな第一歩を踏み出す一助となれば幸甚です。
「はじめに」より 著者を代表して 吉岡 京子
《目 次》
第1章 日常業務での気づきからスタートする事業化・施策化の重要性
1 なぜ専門職は事業化・施策化に取り組まなければならないのか
2 失敗から学ぼう
3 個別支援の経験が事業化・施策化の礎になる
第2章 事業化・施策化のプロセス
1 政策体系の理解:政策、施策、事業の関係性
1) 政策・施策・事業の基本
2) 政策・施策・事業を具体例で理解しよう!
3) 政策・施策・事業の関係性をふまえた事業化・施策化のポイント
(1) 「木を見て森を見ず」にならないように!
(2) 住民ニーズに即した施策化を!
2 政策過程モデル
1) 課題設定
2) 政策(施策・事業)案作成
3) 政策(施策・事業)決定
4) 政策(施策・事業)実施
5) 政策(施策・事業)評価
第3章 事業化・施策化のポイント
1 日常業務での気づきを整理する
1) 「この仕事をやっていてよかった」事例
2) 水難救助の例で考えてみよう
2 なぜその問題が発生しているのか背景を要因分析する
1) 忙しさはいったい何なのか
2) 目の前の事例や認識した問題の背景要因を分析し、真の課題を明らかにするための方法
3 要因分析で陥りやすいピットホール
1) 事業化・施策化に向いている問題と不向きな問題
2) その事例に着目する事で、地域の健康レベルの向上に貢献できるか
3) 「困っているのは誰なのか」を明確化する作業
4) 当初設定された問題が真の問題ではない場合がある
5) 職場の仕組みや関係機関の対応の批判に終始しない
4 根拠を整理する:データ、法的根拠等の活用
5 仲間をつくる
1) 仲間を見つける
2) 組織内で仲間をつくる
3) 仲間を広げる
6 予算を獲得するための方法を理解する
1) どのような予算を使うのか
2) 費用対効果をどう示すのか
(1) 事業費の算出
(2) 事業実施による成果の見積もり
7 自分の仕事の専門性を他職種に理解してもらう
8 事業案作成時に陥りやすいピットホール
第4章 職場で事業化・施策化について検討する際のポイント
1 グループワークの進め方
1) 因果関係図の結果から考える場合
2) 因果関係図の原因について考える場合
3) 事業案の方向性を考える場合
4) 事業案の内容を具体化させていく場合
2 事業化・施策化が困難となる理由
理由その① ないない呪縛
理由その② 地域診断ありきの考え
理由その③ 前例主義の組織文化
理由その④ 諦めの境地
第5章 具体的な事例
1 母子保健
(因果関係図の中心となる事例)
(類似問題を抱える事例)
(因果関係図の中心におく問題)
(原因)
(結果)
考えた事業提案書 78
事業名:育児支援ヘルパー派遣事業 78
2 生活習慣病の予防、健康づくり運動 79
(因果関係図の中心となる事例) 79
(因果関係図の中心におく問題) 79
(原因) 79
(結果) 79
考えた事業提案書 その1
事業名:階段への健康増進メッセージ貼り付け事業
考えた事業提案書 その2
事業名:健康増進員ボランティア育成事業
3 難病
(因果関係図の中心となる事例)
(類似問題を抱える事例)
(因果関係図の中心におく問題)
(原因)
(結果)
考えた事業提案書
事業名:ALS患者交流会事業
4 支援を要する高齢者を潜在化させない早期把握・支援体制整備
(因果関係図の中心となる事例)
(類似問題を抱える事例)
(因果関係図の中心に置く問題)
(原因)
(結果)
考えた事業提案書
事業名:支援を要する高齢者の早期把握システムの整備
最終章 施策化を進めていくために
1 地域ケアシステムの青写真(理想)を描き具現化する力
1) 支援対象者が、どういうふうになればよいのかという青写真(理想像)を描く
2) 理想と現実の間にどの程度ギャップがあるのかを明確化し、目標値を設定する
3) 既存の事業・施策では十分に解決しきれない課題であることを根拠に基づき整理する
4) 施策・事業としての位置付けを検討し、明文化する
5) 当初描いた青写真(理想像)と照らし合わせて、どこの部分がどれだけ進んでいるか(または遅れているか)、さらに強化が必要な部分を明確化する
2 根拠を整理しまとめる力
3 みんなを巻き込む力
1) 1枚紙の資料を作り、みんなで活用する
2) 会議体を設置する
3) スケジュールを見える化する
4) 近隣と一緒に取り組む
4 担当業務は全体の一部であることを意識する力
索引
おわりに
著者略歴
付録 要因分析シート(因果関係図) 事業提案書
《著者一覧》
・吉岡 京子 国立保健医療科学院生涯健康研究部公衆衛生看護研究領域 主任研究官
・塩見 美抄 兵庫県立大学看護学部 准教授
・片山 貴文 兵庫県立大学看護学部 教授
・細谷 紀子 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 准教授
定価 本体 2400円+税 ISBN978-4-904363-72―0 C3047
ご注文、お問合せは、本サイトのMain menuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。
