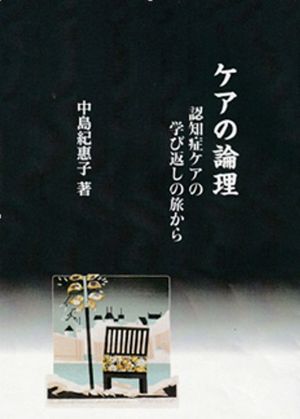
本書の主題は、看護や専門・非専門を問わず介護に携わる者の提供するケアとそれを受け取る者とが関係し合うケアの柔軟さとその実践がもつ義務、つまり、ケアの水準を満たすための努力のあり方について考えることにあります。
私の約40年にわたる認知症の人やその介護家族、そして認知症ケアを進めるには不十分な組織に働く介護施設従事者や訪問看護師、病院で働く看護師、また、大学生や院生などからも多くのことを学んできました。そこで、どんなやり方で、どのように学びをしたか、自分は何をしたか、そんな自分の経験を学び返しながらケアの意味を考えてきました。
それらのことを、皆さんと共有したいと思います。
ケアはつねに進行形です。また、ケアは、介護と同義語として、政治的、政策的な方策に便利なものとして扱われ、時には法的規則とし関わる現場の各領域に異なる意味合いをで通知されるといったことがあります。そういう中では、ケアの意味を問い語り合える共通言語はなかなか育ちません。
しかし、このような中でも、ケアが誰のものか、ケアする者は誰か、これを常に頭に入れながら当事者のニーズをきちんと聴き、語り合いながら関わっている、そして、その様な活動が民主的なプロセスを持って進められている、その様に活動している現場が年々幾つもみられるようになってきました。
私は、満足するケアの水準はその様な活動プロセスにあると思っています。こういう活動のプロセスがあるとき、ケアのそこには倫理性や技術的側面と、教育的、社会的側面や政治的経済的な世界に繋がっていることがみえるようになるはずです。そして自分と自分たちの活動の現在地とそこで期待されるケアの意味を考えるでしょう。
そこから新しいケアの共通言語が作られることを願っています。
本書が、これからの新しい認知症ケア時代の新しいケアのあり方・考え方に少しでも役立つこを願っております。
( 著者 中島恵子)
《目次》
第1章 端緒
生活の質(Quality of life :QOL)が高齢者ケアに与えたインパクト/認知症という世界に関わっていこうと決めた日
第2章 ケアの場を拓く
私の認知症ケアは介護家族の電話相談から始まった/認知症介護の介護を「宙づり状態」に留め置く時間が欲しい/介護家族と共にデイケアを手作りする/日常世界を豊かにするグループホーム/グループホームケアの価値
第3章 自立するという営みとケアの立つ位置
もしかすると、こういうことだったのかも…/認知症の人の潜在能力(ケイパビリティ)/老人の潜在能力
第4章 ケアの共同性と協働の戦略(ストラテジー)
若年認知症の人の主張~新しい支援観が求められる~/「患者」というときの居心地の悪さはどこから/認知症の人の個々の声をきくということ/「認知症の人と家族の会」の分水嶺を越える旅/認知症ケアのイノベーション
第5章 ケアの技(わざ)と術(わざ)の論理
認知症ケアの基本的なかたち/「活動する身体」に込めるケアの技(わざ)と術(わざ)/聴く過程で呼び覚まされる倫理性/振る舞いとしてのコミュニケーションとパーソナルスペース/認知症の人とのコミュニケーションから拓かれる気づきと対話
第6章 居場所
居場所が拓くコニュニケーションのリアル/「居場所」が拓く「在宅」ケアのかたち/「居場所」が拓く訪問看護のかたち/エンド・オブ・ライフ・ケア
第7章 認知症ケアの今日的課題
ケアの核としてあるケアリング/認知症予防と共生をめぐる課題/特養あずみの里裁判が問いかけるもの
終章 コロナ禍の中で
ないまぜの危機のなかで思う~誰もが誰かのケアの担い手~
《著者》 中島 紀惠子
元新潟県立看護大学学長
元日本看護協会看護教育研究センター長
以上
定価 本体2,000円+税
ISBN978-4-904363-93-45
ご注文、お問合せは、本サイトのMain menuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。
送料は1冊でも弊社負担です。発送の際に振替用紙を同封しますので書籍到着後郵便局よりお支払いください。
