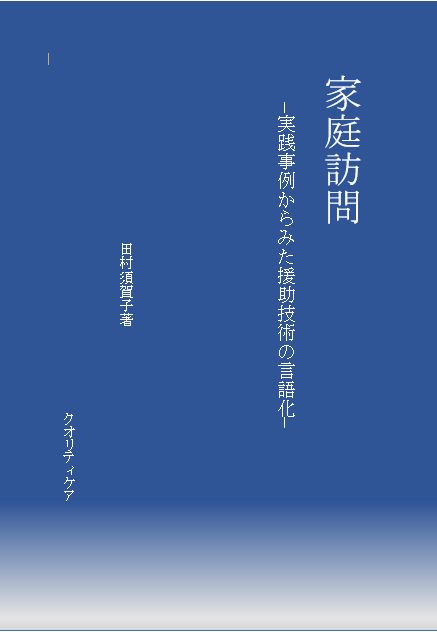
「家庭訪問援助は地域看護の歴史を通して、個別性の高い看護援助方法の中心的存在である」
振り返ると、この一文に看護学生のときから捕らわれてきました。
「保健師は家庭訪問で何しているのか?」ずっと疑問でした。保健師として働き始めた時はもちろん、「保健師としての家庭訪問」ができるようになってきた時も、「それで・・何ができるようになったのか?」と自問し続けても答えられませんでした。先輩保健師に聞いても、「何を聞いているのか」「何が聞きたいのか」という反応で解決しませんでした。
それはそのとおりで「何をどう聞いて、どういう答えがあれば納得できるのか」、自身もわからないまま聞いていたからなのです。
本書は、私のこのような自問自答・試行錯誤の体験から、家庭訪問に潜在する看護実践の本質を「ことば」にして、先達のスキル「技」として残し継承できるようにしたいと思い書き溜めたものです。保健師の家庭訪問援助の言語化・明確化により、優れて特徴的なことを対人援助スキルとして記述し、後に続く人たちにも残し、他の保健師と共有し、互いに高め合えるよう検討できるようにしたいと思いました。
先輩保健師の背中を見て、同行訪問しないと習得できない技の集積。それが保健師の家庭訪問でした。聞いて、見てくる情報量、感度が保健師によって違いすぎました。それはすなわち提供できる支援内容や質の違いとなり、量の大小で現れてきます。「気づく」「気づかない」ではないのです。見ようとしなければ見えない、聞こうとしなければ聞こえないのです。「気づき」に頼るだけでなく、「見ようとすること」「聞こうとすること」、これら一つひとつを保健師の対人援助スキルとして捉え、修得・獲得する必要があるのです。そのために家庭訪問援助の言語化・明確化に取り組んできた私の研究対象の家庭訪問援助事例から、保健師の対人援助スキルとして取り出し整理しました。各ページの上段にスキル「技」として書き出しました。事例と合わせて確認下さい。
《目次》
第1章 家庭訪問援助事例を集める
保健師に援助過程再現事例を書いてもらう/インタビューして筆者が加筆修正する
第2章 会ってもらえる関係づくり
受け入れてもらう/根本原因の腎不全に対応する
第3章 家庭・地域生活に見合った援助提供
生活の場に出向く/音が消えた・消えたから分かった生活の姿/ベビーベッドをどこに置くつもり?片付いてないけど わずかにある家族の関係を切ってはならない
第4章 療養・療養生活上の困難に対応する
「自分で頑張る」って言ったって…「こどもを殺してしまいそうです」/受診はひとりで行けるように…「療育に何の意味があるのか分からない」
第5章 本人・家族ができること・どうありたいか、どうしたいかに配慮する
息子の嫁の介護・月経の世話もする舅―脊髄小脳変性症の療養者の介護力の限界―そうだ人工呼吸器を装着したままで沐浴してみようー医療的ケア児の在宅療養支援/生活機能評価から介護予防サービス参加する前に転倒・閉じこもり―働きづめで燃え尽きるようにー訪問前に認定調査票から療養生活を把握する
第6章 関係職種との連携
担当者会議は集まって合意するだけにする/お父さんはこの子そっくりで―就学後のフォローも見すえての関わり―なんか困っている人いるみたいよ―ごみ屋敷から生活保護担当課の転居命令で1戸建てのアパートに―
第7章 保健事業や福祉サービスへの適用
もう一回頼んでみようよ。必ず来てくれるよ―関わりの未熟な両親への支援―
第8章 保健師の家庭訪問援助はどんな看護援助か
1【前提1】看護援助は看護職がその専門性において責任をもって行うものである
2【前提2】看護援助は提供する者と受ける者との相互作用で成り立つ
3【前提3】家庭訪問援助は当事者本人・家族の援助ニーズを生活の中で把握し問題解決にあたる
4【前提4】家庭訪問援助は第三者が観察できる行為だけでは捉えられない
5.看護援助の成り立ち
6.家庭訪問援助を概観して取り出し統合する
第9章 事例からみる保健師らしい対人援助技術
1.会ってもらえる関係づくりの援助技術
2.地域・社会生活に見合った援助技術
3.療養・療育生活上の困難とその可能性に対応する援助技術
4.本人・家族の能力・希望・価値観に配慮した援助技術
5.関係職種との連携における援助技術
6.保健事業や福祉サービスへの適応に向けた援助技術
以上
定価 本体 2,600円(+税10%)
ISBN 978-4-911097-04-5
ご注文、お問合せは、本サイトのMaine menuの「ご注文⇒オーダーフォーム」、「お問合せ」からどうぞ。
送料は1冊でも弊社負担です。発送の際に振替用紙を同封しますので書籍到着後、郵便局よりお支払いください。
