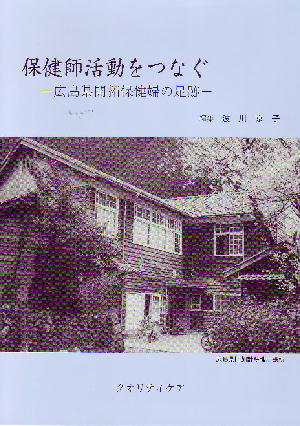 1945(昭和20)年8月、日本を焼土と化した第2次世界大戦は、日本の敗戦で終わった。戦後の開拓事業は、戦禍で荒廃した国土の戦後復興の一環として、海外からの帰還者の就労、国内の食料の増産のために、全国の津々浦々まで農地として開墾することを国家事業とした。
1945(昭和20)年8月、日本を焼土と化した第2次世界大戦は、日本の敗戦で終わった。戦後の開拓事業は、戦禍で荒廃した国土の戦後復興の一環として、海外からの帰還者の就労、国内の食料の増産のために、全国の津々浦々まで農地として開墾することを国家事業とした。
開拓の成功を左右するものの一つに、入植者の健康状態がある。開拓事業は既存の集落、医療施設よりも離れた電気・水・道路などの未整備な土地を切り開いて畑、牧場、果樹園、水田に変えていく労作である。開拓地には希望も、夢もあるが入植者の健康を損なう重労働と生活困難が付随する。
開拓地保健婦は、医療や生活条件に恵まれない入植者に対して、生活実態に合わせた保健指導や健康教育、能力に応じた小集団活動など、対象者のニーズに即した保健活動を実施していた。ここには保健活動の原点(どんな環境であっても健康に着目し、健康づくりを支援する)が集約されている。
開拓保健婦は生産と生殖を担う入植世帯の健康管理のために、開拓入植者の福利厚生事業として制度化された。保健所保健婦、市町村保健婦、国民健康保険組合の保健婦とは別に、農林省の管轄で全国に約300名の保健婦が配置されていた。しかし、国を挙げて取り組んだ食料自給、耕地面積の拡大は、時代の流れの中で農業人口の減少、後継者不足が進行した。
開拓保健婦も1970(昭和45)年に都道府県保健婦に身分移行し、1947(昭和22)年から23年続いた開拓保健婦制度は幕を閉じた。幾多の年月を経て、開拓地は開拓以前の荒野に戻り始めている地域もある。
本書は、戦後の開拓事業がどのように進められ、社会資源が乏しい開拓地で、開拓保健婦が入植者の健康をどのように支え、保健活動を展開していたかを次世代に伝えることを目的としている。
本書を作成するにあたり、開拓事業にかかわってきた元広島県農地開拓課、元開拓保健婦、元開拓営農指導員、開拓地入植者の方々から聞き取りをした。関係者から提供された資料と写真は提供者の要望と同意により、ご芳名を掲載した。
本書における職名は、開拓事業時代の呼称である保健婦を用いた。
2011(平成23)10月 開拓事業終了から40年を過ぎて 開拓保健婦にささぐ (本書「まえがき」より)
目次
まえがき
第1章 公共事業としての開拓事業
1. 開拓事業の目的
2. 広島県の開拓事業
3. 広島県開拓事業の体制
4. 開拓地名の消滅第2章 開拓保健婦の足跡
1. 開拓地の医療
2. 戦後開拓事業と開拓保健婦
第3章 広島県の開拓保健婦
1. 開拓保健婦の職務
2. 開拓保健婦の業務規程
3. 開拓保健婦の研修
4. 開拓保健婦の配置第4章 4人の開拓保健婦
1.宮庄千里氏の開拓保健婦活動
2.石川小恵子氏の開拓保健婦活動
3.岡本夏枝氏の開拓保健婦活動
4.迫 田鶴子氏の開拓保健婦活動第5章 開拓入植者
1.大朝開拓地
2.若林開拓地おわりに
賛辞
在庫がありません。
発行 2011年10月
編集 波川 京子
定価 1,260円(税込み)
