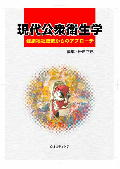|
序
本書の構成や活用法
本書は、公衆衛生学を学ぶ栄養士や公衆衛生看護(保健師、看護師)等の保健医療福祉分野の学生、及び大学院生に必要なことを、公衆衛生の基本的な考え方、マインド、最新の動きや生の実践活動等に絞って紹介し、現代に生きる学生が、今の時代に役に立つような公衆衛生学、必要とされる公衆衛生活動とは何であるかをイメージしてもらうことを目的に構成してある。
現代の公衆衛生学の3代機能は、・アセスメント、・政策、・質の保証、にあるとされる(米国医学アカデミー)が、本書では、健康福祉政策からのアプローチを取ることにした。
本書は公衆衛生学のマインドに重点を置いているため、公衆衛生学の他の教科書と併用することが勧められる。
たとえば、編者は、各分野の基礎的な知識、現代にあっては変化が激しい具体的な法制度や各種の統計数値などの学習には、編者も執筆をしている「公衆衛生」(系統看護学講座専門基礎8、医学書院)等を使用する。
また、公衆衛生の実践活動への導入には、「変わりゆく世界と21世紀の地域健康づくり」(松田ら編、やどかり出版)を使用する。それは以下の理由による。
公衆衛生学は、各国(や各地域)の政治、経済、行政制度、生活(歴史や文化を含め)等と密接に関わりがあり、ダイナミックなプロセスであるため、そのような公衆衛生活動の動態は捉えがたく、本になったとしても、その国や地域、時代背景等を理解していなければ、実感が持ちにくい。
優れた公衆衛生学の教科書であっても、各国の状況をそのまま叙述してある場合、他の国の人には、伝わりにくいことがある。また,同じ国の中でも、時代が変われば、言葉の意味も自ずと重みが変わってくる。たとえば、編者は最近、学生に公衆衛生学の歴史を教えていて、「蚊とハエ」(日本の戦後の有名な住民参加による環境衛生運動)と言ったつもりが、学生には「蚊と肺」と受け取られ、驚いたことがある。
そのため、公衆衛生学の代表的な教科書は、各国や各地域に共通して適用できる、方法論の紹介が中心となってきた。しかし、公衆衛生学を学ぶ学生にとって、方法論が分かったとしても、公衆衛生活動が国や地域の様々な社会的、歴史・文化的な影響を受けるため、そのまま実際の場面で実践できるわけではない。また、方法論は往々にして,読者である学生の興味を引きにくく、無味乾燥なものとなりがちである。そこで本書は以下のような構成を取ることにした。
本書の前半は、編者である松田の、主に静岡県立大学看護学部(内容的には国レベルや国際的な活動も含む)における13年間(1997~2010年)にわたる地域看護の教育や、公衆衛生関連の実践活動への助言の経験からまとめたものである。その経験は、以下のような歴史的背景を背負っている。
昭和30年代に遡るが、静岡県は東京に近いこともあり、「蚊とハエ」の須川医師が県の衛生部長(歴代、厚労省からの出向)をしていた時代に、結核予防婦人会が結成されるなど、多くの公衆衛生上の指導者に恵まれてきた。
その後も、国立公衆衛生院(現保健医療科学院)で歴代の県内の公衆衛生学医師、保健師を研修に従事させ指導者の育成にあたると共に、公衆衛生院からも公衆衛生学医師(西,星,岩永等)が地域活動の指導に訪れている。
また、結核予防会結核研究所よりも医師や保健師が地域の結核対策の指導に訪れ、難病では宇尾野医師が指導にあたり、近年はヘルスプロモーションの指導にも、多くの指導者(島内等)を招聘している。
編者は,大学院生の頃(昭和50年代)に、静岡県厚生保育専門学校の保健師養成コースの先生方(諸井,杉山郁子ら)と丸地教授の研究会に参加し、数多くの保健師と共にプライマリ・ヘルス・ケアの勉強会を行っていた。そのような裾野の広い人材育成の積み重ねの上に、1997年からの静岡での活動には、健康福祉政策学会の諸先生の協力(新井、丸地、山根、石川左門、岩永、塩飽等)で編者の章(特に、本書の「コア・バリュウ」の章、「健康福祉政策の理論と実際」の章)が成立している。
前半の各章は、講演等、筆者の生の声が伝わりやすいものからまとめたものを基本に、本書のために大幅に加筆したものである。筆者の個人史まで含めて述べたのは、考え方や価値の背景となる、生活を理解するためであり、叙述の方法としてナラティブ(語り)と言う要素が入っている。データになれている学生にとっては目新しい述べ方となっていよう。
ナラティブとは、理論と実践、倫理を個人で統合するものである。大きく分けると、3つの内容に分かれ、・感染症予防医療法という、法から人権・倫理を問うもの(感染症法,倫理の章、1997~2000年)、・健康日本21、健康増進法から健康福祉の地域計画への住民の参画の軌跡(コア・バリュ,理論と実際の章,1996~2010年)、・社会保障の変革から個人のケア(筆者の母の介護)への影響を問うもの(変革の時代,在宅ケアの章,2003~2009年)である。
キーワードとしてあげるなら、公衆衛生学のベースとなる、科学、法、技術、地域や方法に加え、理念、社会、倫理を伝えようとしている。現代が多元主義(意志決定のステイク・ホルダーが政府・行政だけでなく、専門職、住民・消費者、企業、NPO/NGO、国際機関等、多様な考え方を持つ集団の相互作用によって社会が成り立つ)になりつつあり、グローバル化の影響を受けていることが、その背景にある。
(静岡での活動の内、時間の都合から、本書にまとめきれなかったものとして、難病の地域ケア、タイの地域看護と国際保健協力、大学での保健師の教育方法、ナノテクノロジーと公衆衛生があるが、今後も機会を捉えて、まとめていきたい。)
また、本書の後半の部分は、学生で公衆衛生学のより専門的な内容を深く極めたいものを対象に、現代を代表する公衆衛生学のテーマを5名の執筆者にお願いした。即ち、現代を代表する健康福祉政策にアプローチしている日本の実践・研究者によって、・幅広い医学・公衆衛生学の学識に基づくメタボリック・シンドロームと糖尿病(塩飽)、・地域のいのちをつなぐ創造的な公衆栄養活動・食育(秋田)、・国レベルで関わった公衆衛生看護・保健師による特定健診・保健指導(西本)、・日本を代表する公衆衛生医師による日本型のヘルスプロモーションの方法「地域作り型保健活動」(岩永)、・公衆衛生看護・保健師による地域におけるヘルスプロモーション計画の実際(古川)、を述べていただいた。いずれも,執筆者の長い経験とともに、その背後にある公衆衛生学の理念、技術を掘り下げた内容となっている。既にまとめられ、発表されていたものに加筆をしていただいたので、学生にわかりやすい内容となっていよう。
最後になったが、本書は、以下のような方の長年にわたる指導、協力の下に作られたものである。その暖かいご支援に心より,感謝したい。
限られた時間にもかかわらず、精力的に編集・出版を後押ししていただいたクオリティケアの鴻森さん、筆者の母の介護からの回復期に出版を通じて支えていただいた増田さん・工藤さん及び故・西村さんらのやどかり出版・やどかりの里の皆さん、静岡県立大学の関係者(星・廣部・西垣・木苗の歴代学長、矢野・佐藤・小寺・木村の歴代看護学部長、地域看護学スタッフの奥野・鈴木・永田など)、静岡地域ケア研究会のメンバーの皆さん、静岡県並びに静岡市・富士市・焼津市・牧之原市、旧清水・由比・蒲原、旧北遠地域(天竜、佐久間)、伊豆の諸地域、日本健康福祉政策学会の理事の皆様。
なお、表紙は自作の立体・色彩を組み合わせたものであり、御指導いただいた東京・すいどーばた美術学院T.A.Pの長谷宗悦先生にお礼を申し上げる。
2010年3月19日 お彼岸の東京にて 松田正己
目次
第1章 公衆衛生学のベースとしての自然史、コア・バリュウとしてのプライマリ・ヘルス・ケア、 ヘルスプロモーション...松田正己
*銘を受けた2001年の基調講演に模して
*ア・バリュウ(初めての海外旅行)
*ベル,クラーク理論の重要性とその課題
*ケアの自然史,ケアの5段階の提唱
*立から協調,対話路線への転換
*ぜタイでエイズ感染が爆発したのか
*たちの周りにある支援態勢を失わないように
*民参加型活動で成果を挙げた静岡の結核予防活動
*策と質の保証...最先端をいくテーマ
*康福祉政策の準備に必要なこと
第2章 公衆衛生の科学と政策,技術と社会の倫理...松田正己
1.倫理と日常性;喫煙を例とした人間社会のルール
2.倫理を巡る三都物語
3.日本;義務としての健康から権利としての健康へ,予防と人権への両立
4.新しい技術と社会の危機統治の枠組みから公衆衛生の新しい倫理へ...ジェフリー・ハント
第3章 健康福祉政策としての公衆衛生と人権の課題─感染症の予防医療法の制定の事例から─ ...松田正己
*衆議院の厚生委員会に参考人として
*法案の奇妙なプロセス
*法案のポイント
*疾病予防と患者の人権のバランス
*審議会の答申と違う法案が
*法律は100年変えられない
*「医学」対「法律」
*竜頭蛇尾(頭は予防医療,尻尾は予防)
*「人権に配慮」と「人権の尊重」は違う
*予防医学の原点を研究
*プライマリ・ヘルス・ケアの登場
*人権と健康
*国際保健
*タイのHIV
*日米の感染症法の違い
*IHRとは何か
*フィドラー教授の来日へ
*国際保健規則の改定
*症状からの接近
*感染症の「水際作戦」は「水漏れ作戦」?
*WHOの感染症対策の基本
*患者の権利
*衆議院厚生委員会で配った資料
*病名の特定は必要か?
*病名は罰則から?
*法律の見通し
*強制は必要か?
*結核予防法との違い
*資料1 死になさい?
*資料2 感染症予防・医療法案に関する意見
*料3 病名分類を廃した感染症予防法を...デビッド・フィドラー
第4章 健康福祉政策とヘルスプロモーションの理論と実際─プライマリ・ヘルス・ケアによる健康格差是正と保健医療福祉... 松田正己
1.健康日本21から健康増進法へ
2.地方分権に向けた健康日本21発展の意義と展望
3.効果的な計画実施
4.健康格差
5.地域の健康福祉政策;静岡の例
第5章 公衆衛生の理念と社会保障のあり方─医療制度改革と変革の時代に求められる保健・医療・福祉─ ... 松田正己
*プライマリ・ヘルス・ケア、ヘルスプロモーション
*感染症予防法は人権問題
*医療や福祉が切り捨てられる時代に生きる専門職として
*「変革の時代」という名の「弱者の切り捨て」
*メタボリック・シンドロームとは
*筆者の母の場合~現代の典型的な地域の家族~
*母の経過
*医療費はかかるというのが実感
*筆者の留守中,転倒し救急車で運ばれる
*母を連れて海外に~死んでも責任は持たない約束~
*毎日,病院に2時間ぐらい見舞う生活
*医療改革を読み解く
*予防対策を設計する場合にどんな人材が必要か
*結核対策が,参考に
*施設は絶対的に不足している
*不十分な介護保険制度
*健康環境,健康教育の必要性
*医療現場の悲惨な状況
*弱者にとって,現代は「鬼の時代」
*メタボリックの対策は,結核予防に学ぶべきことがある
*社会に格差が出てきた時には,ポピュレーション・アプローチは危ない
*2極分化に即した対応を
*構造改革~弱者へのしわ寄せが,医療,福祉に~
*アメリカ~医療の切り捨ての連続~
*日本の医療,すさまじい実態
*医療の構造改革とは「日本が途上国になる」こと
*必要な人を辞めさせないこと、自分が辞めないこと
*理念に立ちもどること
*ウィンスローの公衆衛生の定義
*健康は権利だ
*プライマリ・ヘルス・ケアの4原則=メタボリック・シンドロームの予防活動の原則
*住民参加は20年サイクル
*生命倫理の視点
*たとえ寝たきりになっても花見ができるような社会
*友人のお坊さんと友人の哲学者から
*人の顔を持った保健師(栄養士)に
*人々の苦しみを忘れないで欲しい
第6章 健康、福祉、介護とターミナル・ケア、スピリチュアル・ケア:いのちのケアから社会保障へ─肉親の死と自己の回復─ ...松田正己
*はじめに
*母との介護生活を振り返って
*仕事と介護
*母の状態と対話の仕方
*「人間的に生きたい」
*共生か共倒れか
*遅れている日本の認知症の医療
*医療改革のひどさ
*自己の回復へ
*母の介護体験より感じた「構造改革」の本質
*昨日まで使えたものが,使えない
*介護度5でも,ホームヘルパーは1日3時間しか使えない
*病人を1人抱えたら,家一軒のお金は飛ぶ
*介護難民が増える悪循環
*入院時、体温計は自分で用意
*削減がはじまった医療
*救急の必要性
*「社会保障費カット」は世界の悪い流れ
*グローバル化の意味を改めて考える
*肥満の原因はテレビ・ゲームと車
*グローバル・スタンダードの正体
*グローバル化に対するカウンターアクションを
*健康は人権である
*資料a 氷山(公衆衛生)の一角(臨床)
*資料b サリドマイド(1961年)「あなたは薬害を止められるか?」
*資料c 難病・薬害・スモン(1950~60年代)
*資料d 早期警告と遅れた学び(食と公衆衛生・疫学)
*脚気の基礎知識
*日本の脚気の対策(明治時代)
*早期警告からの学びは遅れる
第7章 糖尿病とメタボリック・シンドローム...塩飽邦憲
1.生活習慣病
2.生活習慣病の危険因子
3.生活習慣病予防の基本
4.肥満者の増加
5.メタボリック・シンドロームの提唱
6.メタボリック・シンドロームの診断基準
7.メタボリック・シンドロームのための行動変容方法
8.行動変容の継続
9.メタボリック・シンドローム対策(特定健康診査と特定保健指導)
10.増加する糖尿病とメタボリック・シンドローム対策
11.メタボリック・シンドローム対策の今後
第8章 医療制度改革と特定健診・特定保健指導...西本美和
1.わが国の医療保険制度と医療費の動向
2.医療制度改革の背景と内容
3.特定健診・特定保健指導
4.専門職としての役割
第9章 人と地域が元気になる共創・協創型の公衆栄養活動...秋田昌子
1.時代の「潮流」と「底流」
2.事例1;複合福祉施設における栄養士の取り組み=「摂食・嚥下ケア」を目指した多職種協働による「食とケア」=
3.事例2;"いのち"を生かし合って生きる人間環境づくりの取り組み=「産学官民」協働による「いのち・つなぐ・"みんな展"」=
4.事例3;"生きがい"を目指した介護予防事業の取り組み=住民,地域団体,NPO等の協働で創った「高齢者いきいき健康教室」=
5.ヘルスプロモーションを「食育」で具現化するチャンスの到来
6.事例4;民・産・学・官による協働・協創の食育推進の取り組み=「つながる」をキーワードに行政主導型から民主体型の活動へ=
7.協働で推進する「食育」を「文化」として育む
8.共創・協創型の人づくりが新たな領域を拓く
第10章 地域づくり型保健活動と栄養士...岩永俊博
1.地域づくり型保健活動の意義と特徴
2.どのような場面で使えるか
3.地域づくり型保健活動の手順
第11章 健康福祉政策の計画方法─フォーカス・グループ・インタビューをプリシード・プロシードモデルで整理...古川馨子
1.フォーカス・グループ・インタビューとは
2.フォーカス・グループ・インタビューの実際
3.インタビュー結果をまとめる
4.結果を計画にどう活かすか?
5.複数のフォーカス・グループ・インタビューのまとめ方
資料 プリシード・プロシードモデルを活用した健康増進計画の策定について
編 集
松田 正己 東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科教授
執 筆(執筆順)
松田 正己 東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科教授
Geoffrey Hunt 英国St Mary's University College 哲学・神学・史学部教授
David P.Fidler 米国インディアナ大学Maurer法学部James Louis Calamaras教授
塩飽 邦憲 島根大学医学部副学部長兼教授
西本 美和 滋賀県大津市健康保険部保健所健康推進課 健診保健指導グルー プ グループリーダー
秋田 昌子 東京都墨田区福祉保健部保健衛生担当 保健計画課保健計画担 当主査
岩永 俊博 社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター常勤顧問
古川 馨子 静岡県牧之原市役所健康増進部健康づくり室主任保健師