新刊情報 ★★★★『在宅看護過程演習ーアセスメント・統合・看護計画から実施・評価へ』
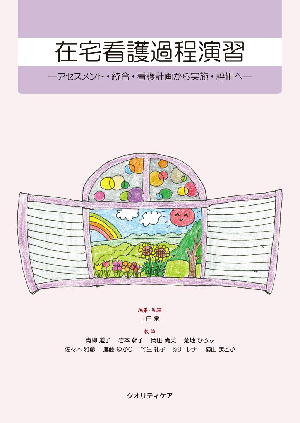 昨今の社会状況では高齢化が進み,入院期間の短縮,在宅医療の推進等の背景により,在宅ケアおよび在宅看護に対する社会のニーズは高まっています。
昨今の社会状況では高齢化が進み,入院期間の短縮,在宅医療の推進等の背景により,在宅ケアおよび在宅看護に対する社会のニーズは高まっています。
1997年カリキュラム改正により,看護の一つの領域として在宅看護論が位置づけられました。さらに2009年カリキュラム改正により,看護の統合と実践のため,「在宅看護論」が統合科目に位置づけられました。講義・演習・実習の一連の看護学基礎教育の重要性が指摘されており,特に在宅看護を実践するという学習のなかで,基本となる看護過程の展開能力をいかに培っていくかは重要な部分であると考えます。
著者らは,在宅看護に関する科目を教授する上で,在宅看護過程あるいはアセスメントに関する参考図書が未だ少ないこと,市内の同じ訪問看護ステーションへ複数の看護系教育機関が実習していますが,使用している看護過程記録の様式も内容も様々である,という現状を把握しました。そこから,看護過程の図書が1冊あるととても便利であり活用してみたいという話に発展しました。
新刊情報 ★★★★『公衆衛生看護学演習・実習(地域ケア実習)~ソーシャルキャピタルの醸成を目指して~』
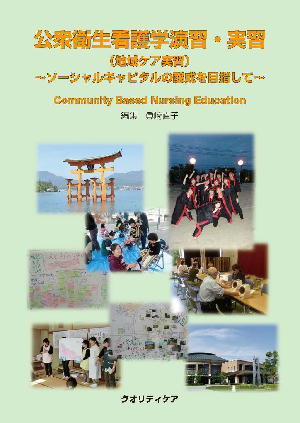
地域の保健活動は時代の変化と共にその重要性を増しています。
平成24年には,「地域保健対策推進に関する基本的な指針」が改正され,ソーシャルキャピタルを活用した住民による自助および共助への支援の推進,地域の特性を活かした保健と福祉の健康なまちづくりの推進等多様な保健活動が提示されています。また,地域の保健事業を担っている保健師の業務について,予防的介入の重視,地区活動に立脚した活動の展開,総括的な役割を担う保健師の位置づけ等が地域保健総合推進事業報告書より提言されました。
平成25年には「保健師活動指針」を改正し,保健師の保健活動の基本的方向性,地区担当制の推進,保健師の総括的な役割および活動領域に応じた保健活動の推進などを定めています。
一方で,保健師教育は,平成22年改正保健師指定規則により,公衆衛生看護関連科目28単位以上,公衆衛生看護実習として5単位が明記された。すなわち,大学の講義や演習・実習においても保健師教育課程のさらなる充実と卒業時到達能力の醸成が求められています。
新刊情報 ★★★★『国際看護学』
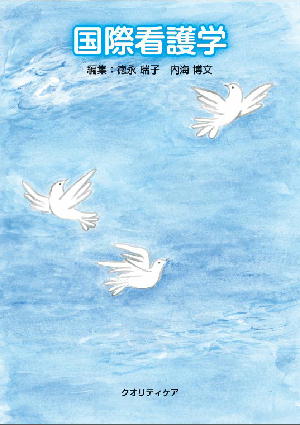 この本のタイトルは『国際看護学』であるが,この本を手にした人は,今まで出版されている『国際看護学』の本とはいささか内容が異なると感じられるに違いない。
この本のタイトルは『国際看護学』であるが,この本を手にした人は,今まで出版されている『国際看護学』の本とはいささか内容が異なると感じられるに違いない。
それは,この本は,8名の執筆者全員が,中央アフリカ共和国に数週間から数十年滞在して,その地で体験したこと,調査したことを基に実体験を書いたからである。執筆者の職業は,社会学者,医師,保健師,助産師,看護師であり,それぞれが専門とする分野に焦点を当てて,調査研究したこと経験したことを記述している。
第Ⅲ部「国際看護学の理解を深めるために」を執筆した内海氏は社会学者で,島国日本から海を隔てる海外諸国の「遠さ」について述べている。グローバル化により世界の情報は机上で簡単に入手することができ,また物理的な距離もハイテクノロジーによるスピードアップや交通網の発達により短縮され便利になった。しかし,日本人にとって海外は,今なお心の距離は短縮されていないように思う。(以下「詳細」からご覧ください)
新刊情報 ★★★★『壮年期生活保護受給者の健康支援』

生活保護受給者への健康調査ということで,社会福祉事務所の生活保護担当ケースワーカーの皆様には,大変お忙しい中,調査のご協力をいただきました。また,調査に回答くださいました生活保護受給者の皆様,市町村保健師の皆様,本当にありがとうございました。 健康格差が指摘されている昨今,平成24年7月には,21世紀における第2次国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))が策定され,基本的な方向として健康寿命の延伸と健康格差の縮小が示されています。居宅の壮年期生活保護受給者はどのような集団なのか,公衆衛生を活動の基盤としている保健師が果たすべき役割は何か,今回の調査結果が住民の声として反映され,保健福祉サービスを検討する際の一助となれば幸いです。
本書の一部は,平成24年度から2年間にわたり,科学研究費補助金の交付を受けて行いました「居宅の壮年期生活保護受給者の健康関連QOLと健康支援のニーズに関する研究」の成果をまとめたものです。 「あとがき」より(抜粋) 2014年夏 富田早苗
新刊情報 ★★★★『在宅看護学』第5刷増補新訂版
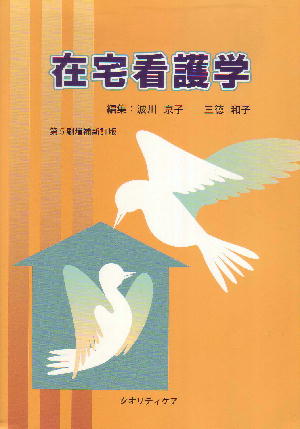
今回の版では構成は変更していないが、内容を大幅に刷新してある。
5章の在宅看護過程は全面的に書き改めた。基礎的な知識を整理してから、事例を学び、在宅での看護過程の理解が進むように構成されている。
9章Ⅳ在宅緩和ケア
Ⅴ地域で暮らす精神障害者の生活を支える看護
Ⅵ在宅で療養する子どもへの支援
10章Ⅴ日常の安全管理
も5章と同じ考えから、全面的に書き改めている。
1章Ⅰ在宅看護の背景
2章Ⅰ在宅看護の基本と特徴
は他の章でくわしく触れられる内容については、概要を述べるように簡略化されている。
また、各章のデータはすべて入手できる限りでの、最新の情報に基づいて書き改めている。
読者の皆様のご意見を踏まえ、よりいっそうの充実をはかりたい。
2016年2月 編者ら
新刊情報 ★★★★『グローバル化・健康福祉政策と公衆衛生・倫理』(現代公衆衛生学第2版)編集;松田正己
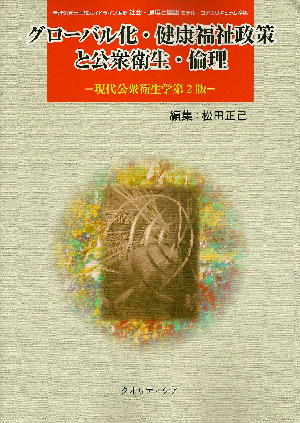
本書は2010年3月の初版の改訂版である。公衆衛生学を学ぶ栄養士や公衆衛生看護(保健師、看護師)等の保健医療福祉分野の学生及び大学院生に必要なことを、公衆衛生の基本的な考え方、マインド、最新の動きや実践活動等に絞って紹介し、現代に生きる学生が、今の時代に役立つような公衆衛生学、必要とされる公衆衛生活動とは何であるかをイメージしてもらうことを目的に構成してある。
今回、3年半という比較的短い時間で、改訂版に取り組むことになったのは以下の理由による。
1.学生に分かりやすくと心がけて初版を作成し実際に3年間使用してみて感じたことは、現在の大学の2年生にとって公衆衛生学は内容が多岐にわたり、社会・世界・歴史等との関連性があるためか、多少、高度であったかと。また、基本的なことの解説が必要であることを痛感した。
2.そこで、改訂版では、授業の中で学生とともに試行錯誤して作り出した、①講義資料の図解、②国試対策につながるミニテスト、③そのための重要事項、を巻末に追加した。これらは、4年生の国試対策でも再度使用するものとなる。また、④疫学・統計については、苦手科目である学生も多いので、新たに章を起こした。これは、主に3年生で使用するものである。
3.この3年の間に起きた社会の変化には、①東日本大震災と福島の原発事故があり、技術と倫理の課題が大きくなってきている。また、②健康福祉政策では、健康日本21の第2期が開始、③国際的には肥満が大きな課題となり、国連がNCD対策に取り組み出し、栄養の重要性が更に高まっている。
4.そこで、改訂版では、新たに①序章、②1章、③8章、④9章を追加し、公衆衛生学の起源と福祉の関係をチャドウイックにさかのぼり検討し、功利主義の克服という倫理的テーマを導き出した。その過程には、英国の19世紀における新救貧法とディケンズという文学者が関係している。更に、2012年11月に行われた日本健康福祉政策学会の会長講演や、タイなど海外での公衆衛生への取組みをまとめてみた。
5.各執筆者にも、原稿を大幅に改定することをお願いし、よりシンプルな内容で、栄養に関連した公衆衛生をめざした。また、新たに4名の執筆者に加わって」いただいた。
(初版及び本書の「序」より抜粋)
新刊情報 ★★★★『コンサルテーションを学ぶ』
 コンサルテーションの大切な機能は、コンサルティの人間的な潜在能力を促進し、一人ひとりのコンサルティ個々の中に自己回復の能力を醸成することである。
コンサルテーションの大切な機能は、コンサルティの人間的な潜在能力を促進し、一人ひとりのコンサルティ個々の中に自己回復の能力を醸成することである。
コンサルタントは、コンサルティが実施するケアを向上するために、相互作用する相談方法を用いることがコンサルタントの専門性である。
コンサルタントは、コンサルティである同僚看護師の看護が向上するためにコンサルターションを行うことで、看護師が新しい環境を患者にもたらし、そして新たな活力をコンサルティにもたらすことが出来る。
新刊情報 ★★★★展開図でわかる 「個」から「地域」へ広げる保健師活動
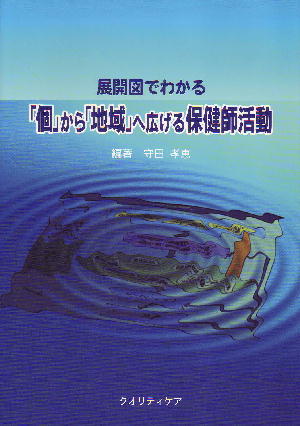
発刊にあたって
筆者が保健師になった動機は、学生の時の実習にある。当時の科目名は「公衆衛生看護学実習」だったのかどうかも覚えていない。しかし、学生である私は保健師の動きに感動し、目の前で、「地域」の力が見たのである。心底、「おもしろい」と思った。保健師活動に魅力を感じた。
私は、東京都内の保健所で実習させてもらった。新聞の第一面を騒がせた感染症が発生したこともあり、保健所の危機管理の実践に身を置くことができた。学生の私たちは、遠目で所内の動きを見ていただけではあるが、その状況は今でも記憶として鮮明に残っている。
当時の私の実習指導者である保健師の主査は、所長、課長と協議を重ね、保健師に指示を出していた。「大変ですね」と声をかけるほかの部署の職員に対して、主査は「こんなに忙しいのにちっとも痩せないのよ」と答えていた。こんな会話もはっきりと覚えている。緊迫した状況にもかかわらず、逆に周囲を気遣う、保健師の懐の深さに私は感動を覚えた。
7 / 8
