新刊情報★★★★『精神科音楽療法ことはじめ ~こころ からだ いのち を紡ぐ音楽療法 ~』
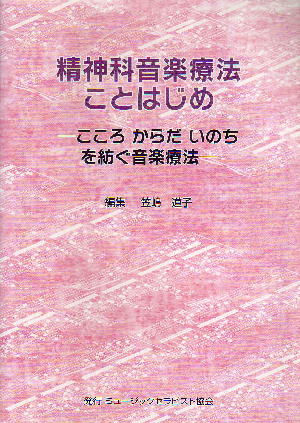
その時は自分には到底無理な分野であると思い,4人の子どもの母親という立場から,音楽療法のスタートとして取り組んだのは児童分野でした。
その後,松井紀和先生にご指導頂き米国音楽療法視察団に参加,メニンガーという世界的な精神科治療の研究団体の視察に加わり,有名な病院の米国の患者様の様子を見学しました。1985年のことです。そこにはお金を十分にかけた,薬物を使用しない治療の方法がたくさんありました。患者様は幸せそうだと思いました。
あれから,縁あって木更津病院,南房州の三好病院を経て精神科の音楽療法に関わりを持つことになりました。
現在,多くの患者様と一緒に音楽をし,変化を体験し,改めて音楽療法の果たせる役割を鑑み,ぜひ多くの方々に精神科の音楽療法を体験してほしいと思いこの本の出版の想いに至りました。技法のところでは,竹内和美,山本名映子と笠嶋道子の3人で行っているセッションについて,各病棟で役割を交互に勤めながら進めている都合上,執筆を連名としました。また,個人的な様子を書いた「こんなことあんな人」の欄は執筆者の名前を明記しました。読んでくださる方々が,精神科の患者様の様々な健康な部分の認識をもって下さり,同じ人として理解あるいは共感を持っていただければ幸いです。
多くの患者様,また病院関係者の方々に感謝を申し上げるとともに,私たちに多くのご指導をくださった昨年ご逝去なさった精神科医吉川武彦先生が,天国でこの本を読んでくださいますよう心から祈念しております。有難うございました。
「まえがき」より 笠嶋道子/2016年7月1日 千葉県君津市に於いて
新刊情報★★★★『保育内容・領域 言葉 演習と講義』
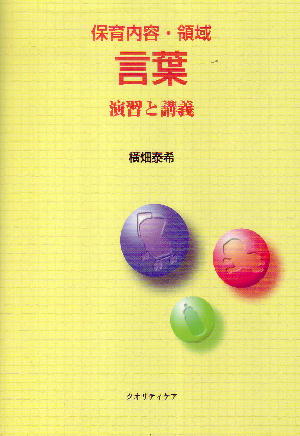
「講義と演習」というサブタイトルは、概論的な内容の講義形式の授業と、指導法的な内容の演習形式の授業の両方を示している。どちらにも対応できる内容であるが、演習形式の指導法の授業の際には、各講に示した演習問題に基づいて考察を深めていけるよう配慮した。
ところで、人間が使う言葉は癒しにもなれば、武器にもなることは周知のとおりである。これは言葉の持つ意味について考えていかなければならないことを示唆している。
たとえば、A児がB児に「そんなん、やめればええじゃろぉ!」と言う。その言葉を発したA児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉を受ける側のB児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉で繋がっているA児とB児にとって、その言葉の意味は何なのか。その言葉を傍で耳に(目に)している保育者にとって、その言葉の意味は何なのか。これらは、言葉の意味を探っているようであり、実は保育そのものだと言っていいのではないか。言葉を育てる保育だけを考えていては、保育の本質を見誤る。あるいは見失う。保育とは、子どもの心と身体を健やかに育てることに他ならない。心が健やかに育つことが、すなわち言葉が育つことに他ならない。
本書、本科目を通して、子どもにとって何が大事なのか、保育者はどうすればいいのかを考え、
保育者としての基礎を培ってもらえたらと願っている。
本書「まえがき」より 橫畑泰希
新刊情報★★★★『保健医療福祉専門職のための 事業化・施策化のすすめ方』
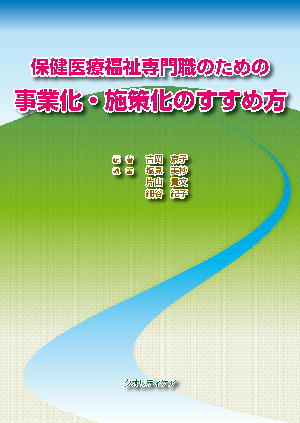
上流から地域の健康問題を支援する ご当地システムづくりをすすめるために
かつて現場で駆け出しの保健師として勤務していた頃、毎日家庭訪問を行う中で「同じような問題を訴える住民」の方にたくさん遭遇しました。私はその頃から「どうすれば住民の健康問題に基づく効果的なサービスを提供できるのか」ということを考え続けて参りました。幸いにも大学院進学のチャンスを頂き、現場のニーズに基づく政策形成をテーマとして、「事業化・施策化」という切り口で研究を始めました。インタビュー調査をさせて頂く中で、次第に「事業化・施策化をすすめるための具体的な方策がある」ということを確信すると共に、現場にはまだ十分に整理されていない暗黙知があることに気がつきました。大学院終了後に再び現場で奉職させて頂くことになり、研究で得られた知見を実践の場で検証する機会に恵まれました。現場で様々な提案や調査をさせて頂く中で、改めて事業化・施策化の方法論について再考すると共に、「事業化・施策化は神業ではなく、専門職の基本的な技術として身につけてほしい」、「専門職が住民や地域の健康問題に即した事業化・施策化を効果的にすすめるためには、知の共有化を図る必要がある」と考えるようになりました。
新刊情報★★★★『PDCAの展開図でわかる 「個」から「地域」へ広げる保健師活動』 改訂版

本書の初版の発刊が 2013 年 3 月でした。その後,4 月 19 日に「地域における保健師の保健活動指針」が改定されました。保健師の保健活動の基本的な方向性として 10 項目が提示され,その一番はじめの項目が「地域診断に基づく PDCA サイクルの実施」です。二番目の項目は,「個別課題から地域課題への視点」です。これらは,まさに,本書で示す展開図の要素です。保健師は日常業務の中で,地域の健康の問題を発見し,地域診断を行い地域保健活動の PDCA サイクルを回しています。その PDCA サイクルのプロセスは,個別の健康課題を地域全体の課題として束ねてみていく視点に基づいています。
本書は,保健師が毎日,あたりまえに見ていることや行っていることを PDCA サイクルに位置づけて,保健師活動指針に沿った意味づけを可能にするツールです。
また,この展開図は,PDCA サイクルを追うプロセスの中に,3 事例を包含しており,この点は他のツールにない特徴的な点であると気づきました。この 3 事例にしっかりと向き合うことができると,地域に必要なことが浮き彫りになってきますし,保健師の中に,「何とかしなければ」という活力が湧いてきます。その活力こそが,地域活動を展開する原動力であると,保健師現任教育に関わる中で実感いたしました。
新刊情報★★★★『ワークブック 地域/公衆衛生看護活動事例演習』
 このワークブックは,大学で看護学を学ぶ途上にあり,将来看護師になろうか保健師になろうかまだ決めていない人,または看護師を目指している人,あるいは保健師になると決めている人,すべての学生に,公衆衛生看護のものの見方や考え方を学んでほしい,そのように考えて作りました。
このワークブックは,大学で看護学を学ぶ途上にあり,将来看護師になろうか保健師になろうかまだ決めていない人,または看護師を目指している人,あるいは保健師になると決めている人,すべての学生に,公衆衛生看護のものの見方や考え方を学んでほしい,そのように考えて作りました。
私たちは長年,大学で地域看護学/公衆衛生看護学の教育に携わる中で,どのようにしたら公衆衛生看護ならではのものの見方・考え方を学生の皆さんに伝えられるのか,試行錯誤してきました。地域看護学/公衆衛生看護学が他の領域の看護学と最も異にする特性は,看護の対象が,個人や家族ではなく,地域/コミュニティであるということです。そして公衆衛生看護を現場で担う保健師は,保健所や保健センター・地域包括支援センター,事業所や健康保健組合,病院・施設・学校などに所属し,さまざまな保健医療職や保健医療職以外の職種,そして看護の対象となる住民とともに働きます。保健師の行動は,一見看護であるとわかりにくい場合があります。保健師の行動が看護であると理解するには,その頭の中を知ることが重要となります。
新刊情報★★★★『在宅看護学』(第6刷増補新訂版)
 第6刷増補新訂版 発刊にあたって
第6刷増補新訂版 発刊にあたって
今回の版では,医療保険・介護保険の同時改定に伴い下記の章・項のデータを刷新し,内容の見直しを全面的に行った。
第1章 Ⅰ.在宅看護の背景
第2章 Ⅰ.在宅看護の基本と特徴
Ⅳ.高齢者虐待と虐待防止
第3章 在宅看護の仕組み
第4章 Ⅰ.2.【■1】家族に関するデータ的分析
Ⅱ.5.地域における医療の連携
第5章 Ⅰ.2.【■1】さまざまな社会資源の具体的内容
第8章 Ⅷ.在宅における服薬管理
第9章 対象別にみる在宅看護の実際
また次の章・項は最新の知見を取り入れ記述内容の改訂を行った。
第2章 Ⅱ.在宅療養者の QOL
Ⅲ.人権の尊重と権利擁護
第8章 在宅看護技術の実際
第9章 Ⅵ.在宅で療養する子どもへの支援
第10章 Ⅱ.転倒予防
Ⅲ.褥瘡予防とケア
読者の皆様のご意見を踏まえ,さらなる内容の充実をはかりたい。
2019年1月
編者ら
新刊情報★★★★『公衆衛生看護活動論 技術講習第3版』
 本書は,第 3 版の出版となりました。第 2 版の出版から 5 年が経過し,多くの法制度の改正がみられることも鑑み,法制度について新たに見直すとともに,演習事例内容についても見直し充実させました。
本書は,第 3 版の出版となりました。第 2 版の出版から 5 年が経過し,多くの法制度の改正がみられることも鑑み,法制度について新たに見直すとともに,演習事例内容についても見直し充実させました。
新たに加えた内容として特筆することは,一部の個別事例の説明の際に見取り図を導入した点です。平成 28 年 2 月に取りまとめられた「医道審議会(保健師助産師看護師分科会保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会報告書)」においては,保健師国家試験に視覚的素材を活用することが述べられ,例として住宅見取り図や図表等のデータをもとに情報を理解・解釈して必要な介入を判断するような問題を導入することが示されています。
このような背景を考慮して,第 3 版においては,住宅見取り図を取り入れ,視覚的素材からの対象事例の理解ができるように工夫しました。鈴木晃先生には見取り図に関するコラムの執筆を依頼しました。
新刊情報★★★★『始めてみようよ 認知症カフェ -浜松市検証事業の継続からみた提案ー』
 1997年オランダで始まった認知症カフェは、2009年にはイギリスの認知症国家戦略として位置づけられるほどに発展した。認知症カフェを認知症の人が集う場として広くとらえると、日本では1980年発足した「呆け老人をかかえる家族の会(後の「認知症の人と家族の会」)が先駆的であったと言える。2000年からは、介護保険制度も無い中でそれぞれの思いから
1997年オランダで始まった認知症カフェは、2009年にはイギリスの認知症国家戦略として位置づけられるほどに発展した。認知症カフェを認知症の人が集う場として広くとらえると、日本では1980年発足した「呆け老人をかかえる家族の会(後の「認知症の人と家族の会」)が先駆的であったと言える。2000年からは、介護保険制度も無い中でそれぞれの思いから
立ち上がった有志が認知症カフェの開設・運営に力を注いだ時代であると言われている。2012年6月厚生労働省はオレンジプランを策定し、その中で認知症カフェは「認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集う場」と定義され、普及が掲げられた。2013年3月には老人保健推進事業推進費等補助金により行われた「認知症カフェのあり方と運営に関する調査研究事業」報告書が開示され、日本の実態の概要が明らかにされた。2013年10月に発表された著名な「京都方式オレンジプラン」策定に影響を与えたと思われるオレンジカフェ今出川が開始されたのは2012年9月であり、京都認知症カフェ連絡会が結成されたのは2014年である。
- 新刊情報★★★★『ケアの論理』認知症ケアの学び返しの旅から
- 新刊情報★★★★『障がい論』文化に即したケア
- 新刊情報★★★★『デスカフェ・ガイド』~「場」と「人」と「可能性」~
- 新刊情報★★★★『 助産師マコ 続・助産師ものがたり 』
- 新刊情報★★★★詩集『アフリカの風』
- 新刊情報 ★★★★老年看護の縦横な語り
- 新刊情報 ★★★★音楽療法
- 新刊情報 ★★★★わが国在宅高齢者の主観的健康感
- 新刊情報 ★★★★在宅ケアシステム
- 新刊情報 ★★★★乳児保育Ⅰ
- 新刊情報 ★★★★現代公衆衛生学
- 新刊情報 ★★★★善き看護 佐藤弘美Last Note
- 品切れ ★★パーソン・センタード・ケア実践報告書
- 新刊情報 ★★★★ボケ介護日誌
- 新刊情報 ★★★★パーソン・センタード・ケア実践報告書・第2集
- 新刊情報 ★★★★ミュージックセラピスト 演習評価
- 新刊情報 ★★★★エビデンス習得のための 看護疫学
- 新刊情報 ★★★★なぜ?できる!わかる!『私の看護技術』
- 新刊情報 ★★★★『 来て! 助産婦さん』
- 新刊情報 ★★★★『認知症予防テキストブック』
3 / 8
